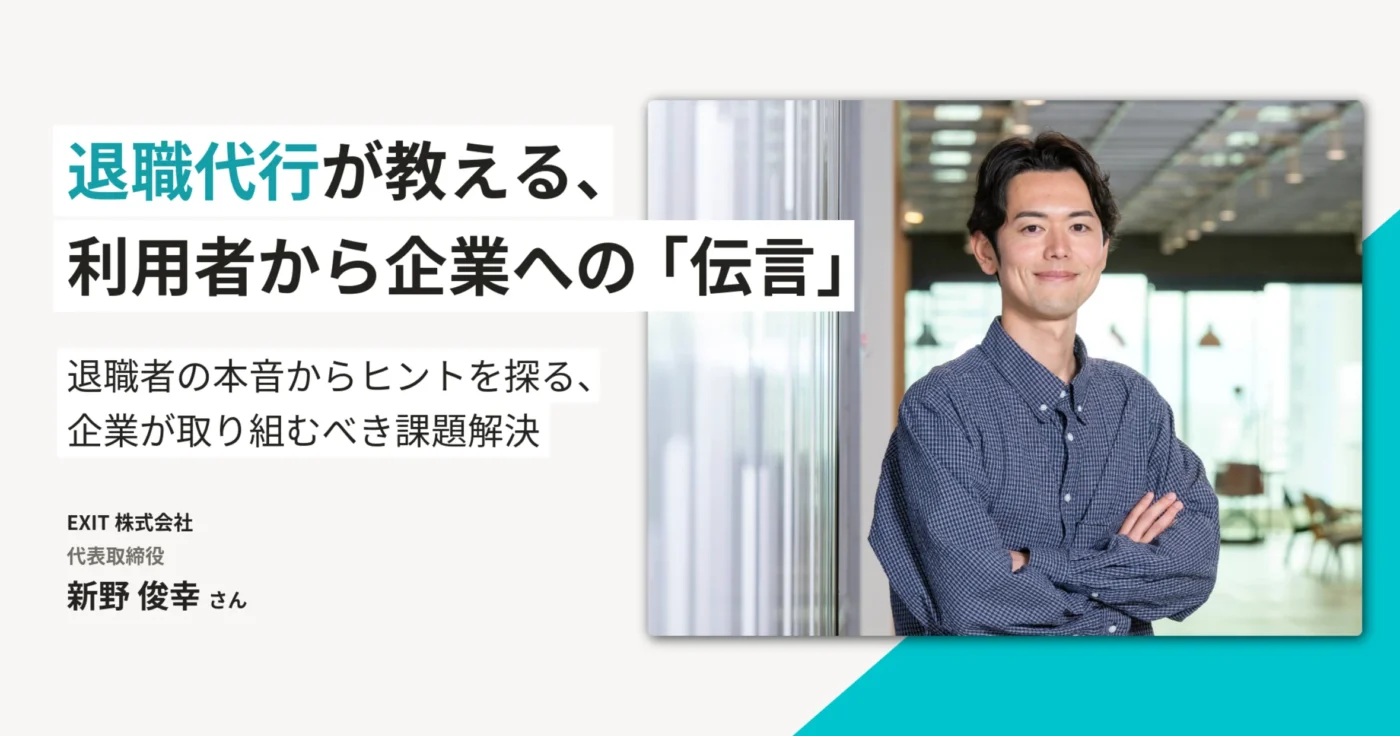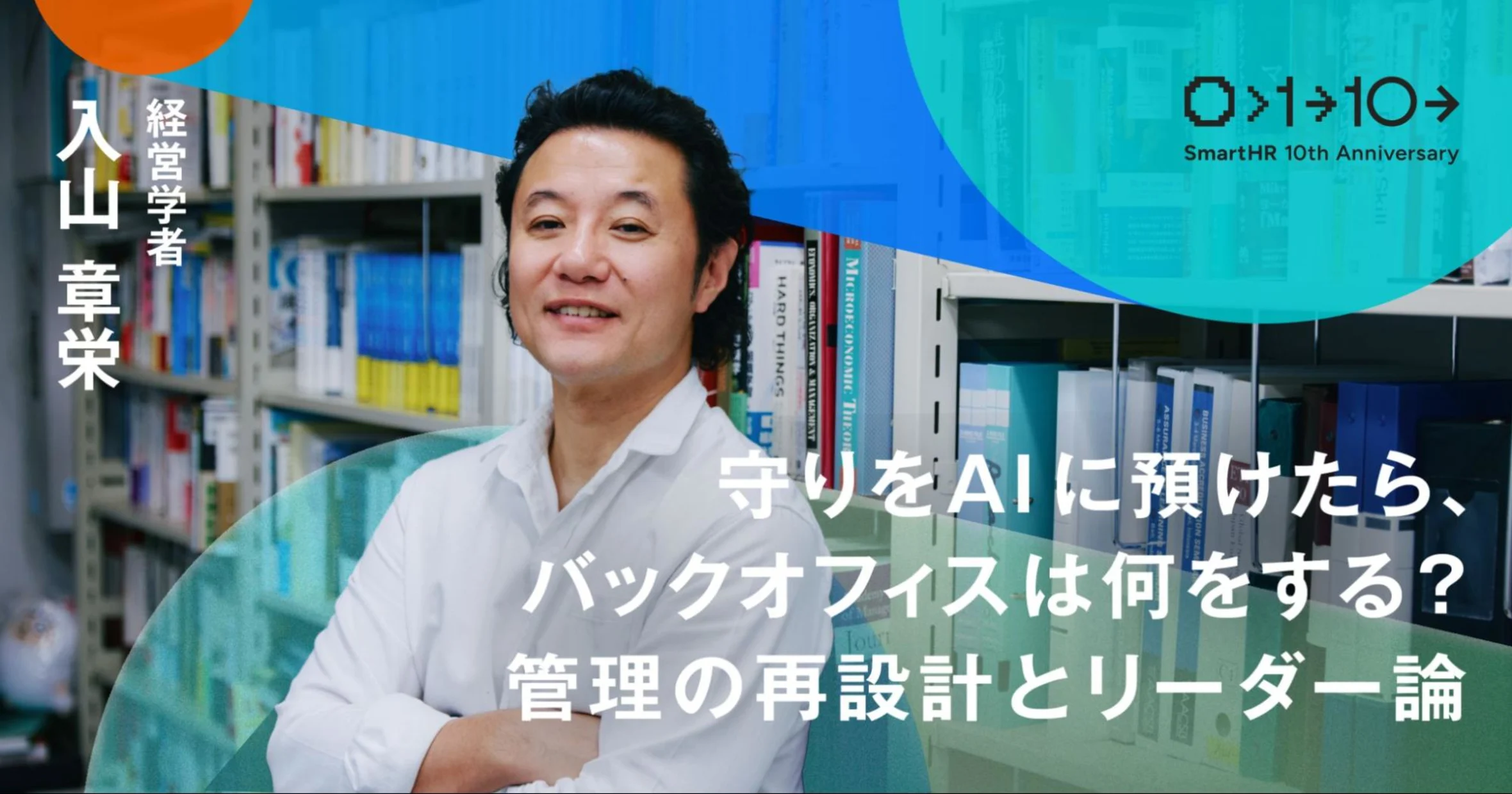不確実性の増大、人手不足、働き方改革、グローバル化に事業承継問題。企業が直面する課題は深刻度を増し、複雑化しています。そうした課題に挑むとき、転ばぬ先の杖になりそうだと注目を集めるのが哲学です。組織運営や仕組みづくりに活かせるヒントを探して、哲学者で著書に『ネガティヴ・ケイパビリティで生きる』(共著・さくら舎)や『増補改訂版 スマホ時代の哲学』(ディスカヴァー携書)などがある谷川嘉浩さんにお話をうかがいます。
変化の激しい時代だからこそ、普遍的な真理を求めるようにして、哲学への関心が高まっています。ビジネス誌で哲学の特集が多く組まれるなど、ビジネスの現場でも注目が集まっていますが、哲学者である谷川さんは、この数年の流れをどう受け止めていらっしゃいますか。
谷川さん
哲学は「ワイルドカード」みたいなところがありますよね。なんとなく、「これまで通りではいけないんだろうな」と思っている人が手を伸ばす先のひとつになっている。
企業に勤める方や経営者の方から、「哲学を学びたい」という声をいただくこともよくありますし、私自身、企業からヒアリングの依頼を受けたり、講演や研修を行う機会も増えました。そうやって、企業の方からなにか言葉を求められたときは、“すこしズラして”答えることが多いです。哲学には、世界のいろいろな捉え方や実践のノウハウが蓄積されていますから、そうした知見を活用して、できるだけ相手の視界には入っていなさそうなことを言えたらと思っています。
谷川さんは以前のインタビューで、「哲学には問いをデザインする側面がある」とおっしゃっていました。企業にも時代の流れを踏まえて、組織のあり方や働き方を根本的に問い直し、変えていく姿勢が求められていると感じますが、どう思われますか。
谷川さん
そうですね。ここでいう「問い」とは、一問一答のように対応する「答え」を欲しがるものではなく、もっと広い意味での「問い」です。言わば「これが気になる」というような“関心の方向性”とか “好奇心の方向性”を示すもの。
この「問い=方向性」という考え方に依拠すると、企業の文脈で似ているものは、たぶんパーパスなんだと思います。
たしかに、「パーパス経営」という言葉が浸透するなど、企業にとって身近な言葉です。経営層はパーパスを指針に企業の進む方向を示すことが重要だとされていますよね。
谷川さん
でも、パーパスって難しいんですよね。これはどんな立場をとるかによって見解も分かれるとは思うんですが、私は「説明的なパーパス」は基本的に良くないと思っているんです。パーパスは従業員や顧客、地域社会とのコミュニケーションの一種なのに、パーパスが複数に分割されていたり、長くて説明的になっていたりすると浸透しにくいし、それじゃあ魅力的な問いが創発されることもないんじゃないか、と。

では、どんなパーパスが理想的なのでしょうか。
谷川さん
私は、パーパスとは「啖呵(たんか)を切るもの」だと思っています。「勢いよく飛び出す歯切れのいい言葉」という意味の啖呵ですね。漠然とした表現になりますが、「なんかよくわかんないけど、なんかすごい」と、惹きつけられるフレーズであることが大切だと思うんです。
たとえば、Appleの「Think Different.」や、株式会社スマイルズの「世の中の体温をあげる」などは、それだけでは意味を完全に理解できないかもしれません。でも、「なんか格好いい」と惹きつけられたり、「なんとなくそれって良さそう」と謎に感化される気がしませんか。
そんなパーパスは、会社にとって良い“方向性”を示すものになり、うまく機能するようになるんじゃないかと思います。だから、パーパスは短い啖呵的な言葉遣いがいい。
もちろん、もうすこし説明したいことがあるなら、パーパスとは別にステートメントを置くのも良いと思います。
そうした羅針盤的なパーパスを通して、社員一人ひとりが問いを立て、仕事のあり方や働き方を考え直すような企業文化ができていくといいのかもしれませんね。
とはいえ、たしかなパーパスがない場合や、あっても企業文化の醸成につながっていない場合はどうしたらいいのでしょうか?
谷川さん
そうですね。今「企業文化」という言葉が出ましたが、私は文化とは「習慣の束」だと思っているんです。
どんな仕事でも、なんらかの法則に従って一定のリズムを刻んでいれば、人は「次はこうなるよね」と予測できるようになりますよね。たとえば、「年度末にはこんなことが起こりがちだよね」とか、「こういうときにはこんな人と一緒に組むといよね」とか。そういった考え方や行動の習慣を束ねてできあがっているのが「文化」である、というイメージです。
社会の文化をつくるとか、それこそ大企業の組織文化を醸成するというとき、いきなり全体の文化を丸ごと変えたり、新しい文化を全体に浸透させようとするのは無理がある。社会でも組織でも無数の習慣が一緒くたになった「文化」をもっているわけですから、いきなり全体にアプローチしても、総体はなかなか動かない。むしろ「変えられない」無力感に襲われかねません。
でも、バンドルされている(束ねられている)習慣の一つひとつは、実はすごく小さなことなんです。その1個なら、変えることだってそんなに難しくない。
だから、会社「全体」とか、習慣の束「全体」を漠然と眺めるよりも、まず1個の習慣を見るとか、経営者自身の習慣を変えるみたいに、まずは小さなチーム単位で習慣を検討するクセをつけるといいと思います。そういう分割的なアプローチのほうが、「文化を変える・つくる」ことによる変化や効果も観測しやすくなると思います。
もちろん、ひとつ変わったからといって、劇的になにかが変わるわけじゃないですけど(笑)